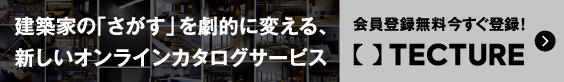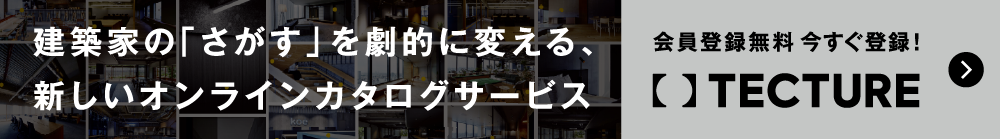PRODUCT

世界で増え続ける廃プラスチックの量は、過去20年で2倍以上に増加している反面、リサイクル率はわずか9%。日本でも24%にとどまっており、その背景には再資源化の難しさがあります。
プラスチックをリサイクルして新しい製品をつくるためには、プラスチックの種類別に分ける必要がありますが、種類の多さや、特殊で高機能なプラスチックの開発などによって素材の分別が難しくなり、家庭レベルでは十分に対応できなくなっている現状があります。
そのため、このようなプラスチックの再資源化は難しく、ほとんどが焼却や埋め立て処分されています。

©︎LIXIL
LIXILは、限りある資源を有効活用しサステナブルな未来へとつなげるため、国内で再資源化が困難とされてきた76%の廃プラスチックに着目。この廃プラスチックと廃木材を組み合わせることで、循環型素材「レビア」を開発しました。
独自の微粉砕化の技術とそれらを均質化する特殊な押出成形の技術により、これまで再資源化が難しいとされてきたほぼすべての廃プラスチックを、再び素材として生かすことが可能になりました。
また、「レビア」のリサイクル技術は、従来焼却処理されていた場合と比較して約80%のCO2排出量の削減に貢献しています。さらに、一度使用したレビア製品を回収して新たな「レビア」として再利用できるといった水平リサイクル*が可能。脱炭素社会の実現に向け、資源循環の推進と環境負荷低減が期待できる製品となっています。
* 使用済みの製品を資源として再利用し、再び同じ製品に生まれ変わらせるリサイクルシステム。(リサイクル可能な回数には限りがあります)
大阪・関西万博「EARTH MART」パビリオンにおいてレビアが採用
また、「レビア」を使用した舗装材「レビアぺイブ」が、大阪・関西万博のテーマ事業「シグネチャープロジェクト」の中のひとつ、「EARTH MART(テーマ:いのちをつむぐ)」パビリオンにおいて採用されています。
本パビリオンは、小山薫堂氏がプロデュースし、隈研吾氏が建築デザインを担当。「食」を通じて、いのちの循環を考えることのできる展示空間となっています。限りある資源の中で、人間が自然と共により良い関係を築くためには、ただ恵みを享受するだけでなく、次のいのちへとつなげる意識が欠かせません。自然と人間が「循環」という関係で結ばれているからこそ次世代のいのちが育まれていきます。
環境と人間のつながり、「循環」を象徴する素材として、屋根には伝統的な循環型素材である茅葺きが採用されました。解体後には畑の堆肥や家畜の飼料として再利用される仕組みです。
この屋根に対して、地面の素材として採用されたのが「レビア」です。持続可能な未来に向けた新たな選択肢として、パビリオンのテーマをより力強く体現しています。
パビリオンでは、日本人が育んできた食文化とテクノロジーによる食の最先端を提示します。建築では、共にリサイクルという特徴を持ち合わせた、伝統的な素材 『茅』と新素材『レビア』が出会いました。そこには、日本人が大切にしてきたサーキュラーエコノミーの伝統と未来があります。そういった意味ではこのパビリオンにぴったりの素材が集まったと思います
「EARTH MART(テーマ:いのちをつむぐ)」建築デザイン担当 建築家 隈研吾氏コメント
(株式会社LIXILwebサイトNEWS 2023年10月号『新建築』より抜粋)

「レビア」は使用後のプラスチックの調達から、再資源化、生産、販売、施工、再度回収するまでのエコシステムを確立することを目標に掲げ、持続可能な社会の実現に向けた一翼を担う素材として、「レビアペイブ」だけでなく、今後さまざまな用途へ応用できる製品としてシリーズが拡充されていく予定です。
トップ画像: ©︎LIXIL