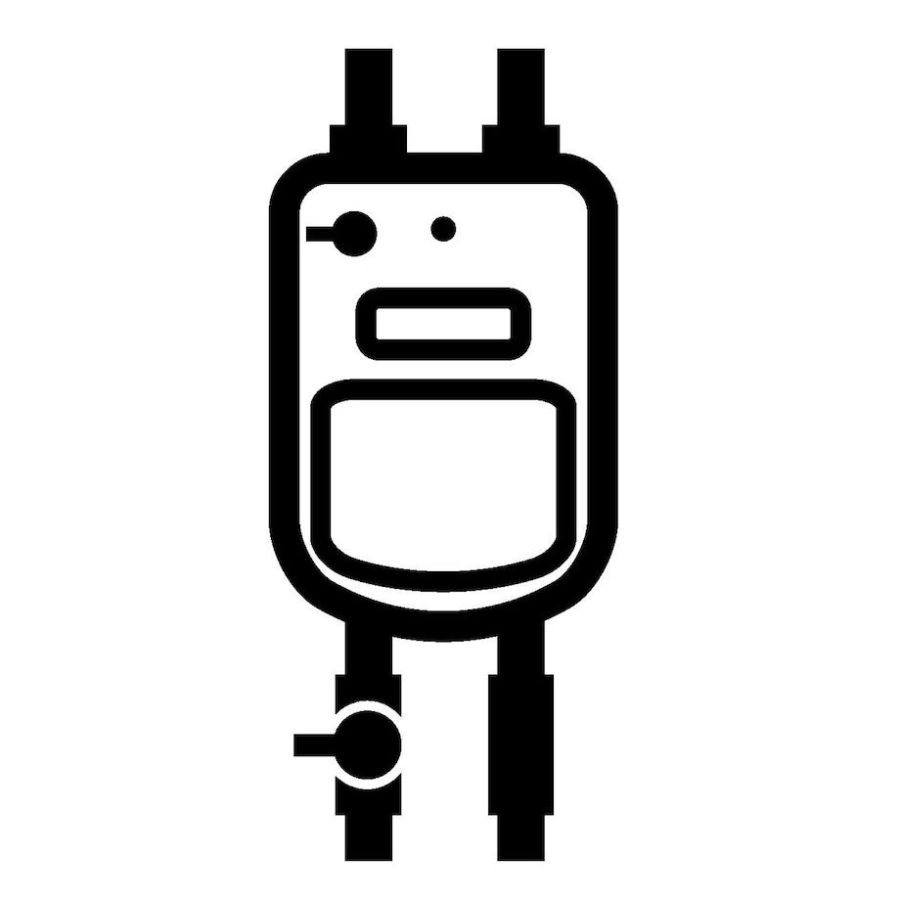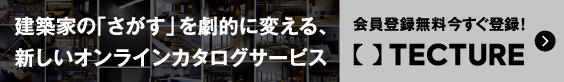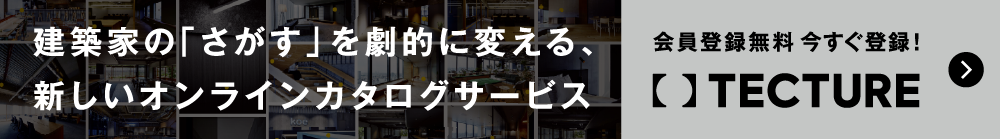BUSINESS

オフィスを中心に、「はたらく」「まなぶ」「くらす」に対して価値創造と課題解決を包括的に進めるコクヨ株式会社。
4月に開催された世界規模のオフィス家具見本市「オルガテック東京2023」(会場:東京ビッグサイト)では、「いっしょにつくろう。」をキーワードに、デジタルファブリケーション技術を活用したオリジナルの内装空間やアート、家具づくりの取り組みを展示。
デジタルファブリケーション技術のノウハウや加工・製作のプラットフォームを持つVUILD株式会社とコラボレーションすることで、従来の“作り手”と“使い手”という垣根をなくし、さまざまな顧客ニーズに応える「共創型オフィスソリューション」を提案しました。
コクヨのブースは、出展各社ブースを対象として、コンセプトやデザイン性等の観点で審査員による審査を行う「オルガテック東京2023 ベストプレゼンテーションAWARD Supported by ELLE DECOR」のグランプリを受賞(2023年4月27日コクヨプレスリリース)。
デジタルファブリケーションを活用したものづくりの実際と、関わったデザイナーの意見から、新しいものづくりと未来のワークプレイスのあり方を紹介します。
(人物写真=TECTURE MAG、それ以外の写真=コクヨ提供)
共創プロダクトとは!?
コクヨ製品のパーツや設計を活かしながら、ShopBot ※(ショップボット)で加工した木材と組み合わせたプロダクトのこと。以下に、代表例をいくつか紹介します。
※ VUILDが日本で代理販売を行うデジタル木加工機の名称コクヨ製の灰皿に、ShopBotで切り出した天板を組み合わせたテーブル
コクヨ製のクッション座面に、ShopBotで切り出した背板(カーフベンディング加工)を組み合わせたベンチソファ
コクヨ製のクッション座面に、ShopBotで切り出した木フレームを組み合わせたチェア
コクヨ製のスクールデスクフレームに、ShopBotで切り出した座面を組み合わせたラウンジチェア
コクヨ製の吸音パネル用フレームに、ShopBotで切り出した合板(コーティング加工)を組み合わせたホワイトボード
新しいものづくりの誕生を祝う会場
今回の会場での「共創プロダクト」の展示で示されたのは、デジタルファブリケーションの活用により、デザイナーや設計者だけでなく誰もがものづくりできるようになること。
作り手と使い手の垣根がなくなった“新しいものづくりの誕生を祝おう”という意味を込めて、会場のコンセプトは「祭」とされました。
「祭」は老若男女誰しもが参加できるもの。今回の会場でも、まさに「祭」のように誰もがものづくりに参加できる場となるようにデザインされました。
「共創型プロダクト」の展示と合わせ、実際にShopBotを稼働させる「参加型ワークショップ」を通して、「自分でもできそう!」「私ならこうつくる!」といった創造意欲を引き出し、ワークプレイスづくりを後押しするような体験が生まれました。

会場に出現した高さ約3mの提灯
空間要素もShopBotを活用し構築
「祭」を象徴するやぐらや提灯といったモチーフ、展示台やアート、サインも、ShopBotで切削した合板の組み合わせでデザインされています。特殊な工具は不要で、主に「組む・つなげる・乗せる」といった簡単な所作で組み立てられます。
同時に、解体が容易であることも大きな特徴です。一般的には、こういった展示会場の内装は会期終了と同時に廃棄されることが多いのですが、今回の展示ではほぼすべての部材を廃棄せずに回収し、コクヨのショールームなど他拠点で活用するなどの2次利用を行っています。製作から使用、その後の展開までサステナブルな活用ができるということも、今回コクヨが目指したテーマの1つでした。

約900mm立方をモジュールとしたやぐら。水平垂直に自由に組むことができ、会場において求心力のある展示台として機能

やぐらのディティール。線材をビスケットジョイントと呼ばれる部材を介して継ぐ。組む・つなげる・乗せるといった簡単な所作で組み立て / 解体が可能

天板を乗せて展示台としても活用

LGSを木で構成したパーツに差し込むことでデザインされたカフェカウンター。背面は合板にShopBotのルーターの切削痕を描いたアートパネル。KOKUYOとVUILDのイニシャルがモチーフになっている

カラーMDFを切削することで会場の展示サインも製作

会場内には実際にShopBotが設置され、ワークショップと連動しながら実際にその場で切削のデモンストレーションが行われた
「いっしょにつくる。」という世界観を、これからのワークスペースに活かしたい
今回の展示で主に空間デザイン・アートディレクションに携わった吉羽拓也氏(コクヨ株式会社 ワークプレイス事業本部クリエイティブデザイン部)に、プロジェクト全体を通じて得た気づきや展望を伺いました。
── VUILDとの協働でのものづくりで心がけたことは何でしたか?

吉羽拓也氏。東京・品川でコクヨ株式会社が運営する「働く・暮らす」の実験場「THE CAMPUS」前にて
吉羽:既製品がない状態からアイデアを出し合い、ShopBotでさまざまな家具をつくっていくことは刺激的でした。「人が集まりやすくなるプロダクト」を軸に案を出し、柔らかく見えて親しみやすいスケール感としました。また、部材のプロポーションを少し大げさにするなどして、家具自体がキャラクターとして感じられるようにもデザインしています。

コクヨ製のクッション座面に、ShopBotで切り出した側板 / 背板を組み合わせたソファ

コクヨ製の背クッションとチェアフレームに、ShopBotで切り出した棚を組み合わせたラウンジチェア

積層したCLT合板の塊を、コクヨ製チェアの座面の3DデータをもとにShopBotで切削したスツール

タイヤに見立てたコクヨ製の吸音アクセサリに、ShopBotで切り出した棚を組み合わせたワゴンカート
吉羽:私たちは「半製品」と呼ぶようになりましたが、部分的にコクヨの家具のパーツや曲面を使いながら、ShopBotで切り出した部材を組み合わせてオリジナルの家具をつくったことが特徴です。例えば、椅子の脚に付けるキャスターは高い機能性と耐久性が求められます。こうした安全基準が求められるような個所や構造的な部分では既製品を用い、それ以外の部分をShopBotでつくる“ハイブリッドのつくり方”は、既存の製品開発のアプローチとは異なり、家具デザインのブレイクスルーになり得るのではないかと思います。
── 展示の方法やつくり方に対する来場者の反応はいかがでしたか?

「THE CAMPUS」内にて。「オルガテック東京 2023」で使用された家具などが一部展示されている
吉羽:ShopBotを活用してつくり出されるプロダクトは、プロセスとともに展示しました。来場者は、自分がスケッチしたものがShopBotですぐにできると、すごく喜んで「持って帰りたい」と口にする方が多くいました。デジタルファブリケーションで、作り手と使い手の垣根がなくなることが狙いでしたが、これを身をもって実感しました。
今回、プロダクトを乗せる展示台や空間を構成するモチーフも線材でデザインし、木槌があれば誰でも組めるようにしました。「自分でもできそう」という来場者もいて、内装としての広がりや可能性も伝えられたと思います。次はドアなど、家具からスケールを大きくしたものもつくっていたいですね。今回の活動を通じて得られた「いっしょにつくろう。」という世界観を、これからのワークスペースづくりに活かしていきたいと考えています。
(2023.07.06 「THE CAMPUS」にて)
コクヨブースには8,300人が来場
「オルガテック東京 2023」のコクヨブースには会期3日間で述べ8,300人が来場しました。会場では共創プロダクトのほか、参加型ワークショップが企画されました。ワークショップでは、来場者が自由な発想で想像するスツールやテーブルなどの家具をスケッチに起こしたり、そのスケッチをもとに ShopBotで実際に製作までを体験するといった体験が提供されました。
VUILDのスタッフがコーディネーターとなり、ワークショップを主導
ShopBotで実際に製作までを体験できるワークショップでは、加工データ自動生成ソフト“EMARF” を使用。EMARFは、VUILDが提供するクラウドサービスの名称で、つくりたい家具のデザインをCADソフトでつくり、プラグインを適用することで木材の加工データを自動生成することができる
来場者それぞれが「つくりたい!」「あったらいいな!」「ほしい!」をスケッチにできる展示コーナー
来場者からさまざまなデザインのスケッチが集まった
会場にはShopBotで切り出したアートピースが配布され、来場者が自由に積み上げることのできる参加型アートも準備された
単純な幾何学図形で構成されたアートピースは、組み合わせの可能性を予感させ、自分でもできそうという創造意欲を喚起させてくれる
EMARFによってつくられた加工データをShopBotで切り出し、コクヨ製のスツールフレームに取り付けることでオリジナルの家具が制作される
スツールの座面程度であれば、およそ2分程度で切削が完了する
切り出された後の合板そのものも、どこか可愛らしくアートピースのよう
プロジェクトチームプロジェクト監修:コクヨ(植田 隆、加藤田歌)
プロジェクトリード・マーケティング:コクヨ(成 濬、廣津志保、平岩和夫)
製品デザイン・プロダクトディレクション:コクヨ(鈴木正義、青山友海、渥美 航、福島拓真、富嶋菜々香)
空間デザイン・アートディレクション:コクヨ(吉羽拓也、池田祐弘)
クリエイティブ&テクニカルサポート:VUILD(山川知則、黒部駿人、木村玲大、金子俊耶)
施工・エンジニアリング:博展(田口幸平、武井俊樹、山本 聖、川島滉市)
ロゴ・コピー・キービジュアル:ダイアモンドヘッズ(望月紀水子、戸次乃里子)
3Dモデルデザイン:清水里紗子
撮影:堀越圭普、鈴木正義