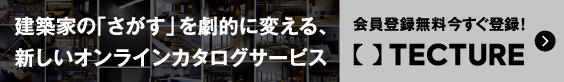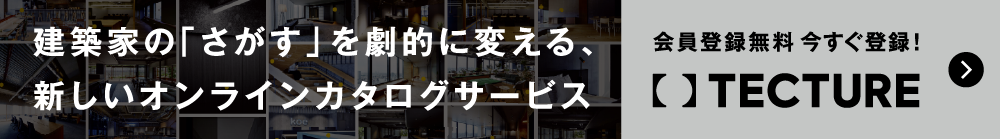![[大阪・関西万博]海外パビリオン紹介_カナダ](https://magazine-asset.tecture.jp/wpcms/wp-content/uploads/2025/04/24195607/rIMG_8911-900x675.jpg)
CULTURE

大阪・関西万博がいよいよ4月13日に開幕。9日には「メディアデー」として、大阪・夢洲の会場を報道陣に公開しました。
TECTURE MAGも、編集メンバーが訪れて会場を体験。感想を語り合いました。
各国のパビリオンや大屋根リング、トイレ・休憩所・ステージなどに建築家が関わるなか、どの施設が印象に残ったのか?
建築の見どころやおすすめ施設を一部、紹介します。
Photo: TEAM TECTURE MAG
視点の変化を楽しめる大屋根リング
kt:初めて訪れたenさん、第一印象はどうでしたか?
en:いやー、広いですね。とても1日では回りきれない。メディアデーは最低でも2日ほしかったです。

kt:まったく同感。万博史上、最もコンパクトな会場と言われているけど、見どころがありすぎて。あの日は会場内だけで、2万歩をはるかに超えました。大屋根リングについてはどうですか?
en:登った時に反対側にいる人の姿が小さく見えるじゃないですか。あそこまでどれぐらいあるんだろう、と呆然としました。

oz:確かに。1周が約2km・幅が約30m・高さが約12mと20m・内径が約615m・外形が約675mですね。上下を繋ぐエスカレーターやエレベーターは数カ所ずつ設置されているけど、せっかくなので屋根の上を1周してみると、30分ぐらいかかりました。
ym:近くで見ると「なんだ?」という巨大なスケールに感じたけど、海側のステージ側では構造体が海の上に浮かんでいるような見え方をして、良いなと思いました。屋根に上がってみると視点が変わって、また違うスケールで感じられるのは面白かった。リングの中を見ると、けっこう雑多に見えたけど。

kt:外側では海が広がり、内側ではいろいろなパビリオンがひしめき合って、それはそれで良い光景だなと思いました。リングの規模や強い求心性については、皆さんが体験してから、またいろいろな意見が出てきそうですね。

百花繚乱のパビリオン
kt:万博会場に入ると、お祭り的な高揚感があり、各国や団体、企業が全力投球で自分たちのアピールの場としている。パビリオンはそれぞれのプレゼンテーションや商談の場となっていて、「そうか、万博ってそういう場なんだな」と実感しました。
ym:開催期間の半年間は明らかに、世界中で最もホットな場だよね。僕は今回パビリオンはほとんど見ていないけど、NOIZが設計した“null²(ヌルヌル)”の〈落合館〉は面白かった。

kt:あのパビリオンは生きているような動きをするので、ぜひ体験していただきたいですね。シグネチャーパビリオンでは自分は、周防貴之さんが設計した〈河瀨館〉が、モノが持つ力にアクロバティックな操作が加わって、強く印象に残りました。

en:私は坂茂建築設計が設計した〈ブルーオーシャンドーム〉がイチオシですね。カーボンファイバーをはじめとした3つの材料からつくられたドームに、原 研哉さんの展示がバッチリとハマっていて。

坂茂建築が設計する万博パビリオン、紙・竹・炭素繊維を用いた“廃棄物ゼロ建築”で海洋問題を啓発:2025年大阪・関西万博 民間パビリオン〈ブルーオーシャンドーム〉概要
kt:パビリオンはどうしても、外観の箱と展示空間が切り離されて計画される傾向にあるので、構造から展示までが一体となっていると建築・アートファンとしては気持ちがいいですよね。
oz:外と中の融合ということでは、〈日本館〉(総合プロデューサー:佐藤オオキ、基本設計・実施設計:日建設計)が予想以上に良かったです。展示内容も、気合が入っていて。


あとは〈フランス館〉が印象的でした。フランス国内ブランドのタッグで、あれだけリッチな展示を実現できるとは驚きです。

kt:映像や外部を組み合わせた構成は、圧巻でしたね。ルイ・ヴィトンのコーナーをデザインしたOMAの重松象平さんには現地でインタビューをしたので、記事をお楽しみに。
〈チェコ館〉は螺旋状のスロープでぐるぐると屋上まで登ることができて、建築として楽しめました。

2025年大阪・関西万博〈チェコ パビリオン〉概要:Design by Apropos+ Tereza Šváchová +Lunchmeat studio
oz:あとは〈バーレーン館〉も、建築の立ち姿がよかったです。

kt:リナ・ゴットメさん設計のパビリオンですね。小耳に挟んだところでは、当初の案に対して、彼女は日本で入手しやすい規格材を教えてもらい再び設計したそうです。外と中ということでは、SANAA設計の〈宮田館〉は、中をつくらないことに振り切っていて、爽快感がありました。

oz:TECTURE MAGでは構造が面白かったもの、ファサードが面白かったものと、パビリオンをまとめながら紹介したいですね。
en:あと、どのパビリオンでもサスティナブルだけでなくリサイクルやリユース、移設についての言及があることは、とても現代的だなと感じます。
kt:ドイツやウズベキスタン、サウジアラビア、カタールのパビリオンも中が良さそうだったけど、時間の都合で見学できなかったのは残念。パビリオン内部のツアーも参加すると、1館で20〜40分はかかります。パビリオン体験は、丸1日で3〜4館じゃないかなあ。万博の建築を堪能するなら、1週間通っても足りないくらいだと思います。
伊東豊雄さん設計の〈EXPOホール(シャインハット)〉、平田晃久さん設計の〈EXPO ナショナルデーホール〉も、まだ中をじっくりと見ることができていないし…。


「大阪・関西万博」迎賓館・大催事場・小催事場のデザインイメージ公開、日建設計 大阪オフィス、伊東豊雄建築設計事務所、安井・平田設計共同企業体が基本設計を担当
多種多様で純粋に建築を追求したトイレ
kt:若手建築家20組が携わったトイレ・休憩所・ステージは、TECTURE MAGとしては注目です。9日には若手建築家たちが、審査員の藤本壮介さん、平田晃久さん、吉村靖孝さんと巡るツアーをしていて、ymさんも見学していましたね。

ym:皆さんの説明を聞きながら見て回ったのですが、普通に面白かったです。TECTURE MAGでもそれぞれの設計でのプロセスを聞いたり、深掘りしていきたいね。
en:20組の施設だけを巡っても、十分に面白いですよね。会場全体に分散しているから大変だけど、お目当てのパビリオンなどとセットで見ていけば、楽しめるはず。20施設について、4つのエリアに分けてガイドとなるレポート記事をつくったので、予習していただければ。
[大阪・関西万博Reoort]若手建築家が設計したトイレ、休憩所、展示施設、ギャラリー、ポップアップステージ、サテライトスタジオなど20施設をエリアごとにまわってみた!
kt:トイレやステージは特に、パビリオンとは違って純粋に建築デザインを追求している印象を受けました。
ym:ただ、トイレのブースが新しい建築空間と一体になっているものは限られていたかなあ。あとは、単体ではとても面白くて、例えば地方にあればとても良いのだろうけど、万博では周辺の状況が特殊だから難しいなと思いました。
あと、竹でつくられたベンチがいくつかあったのは、誰のデザインだろう? あれはよくできていると思います。

en:確かに。知っている人がいれば教えてもらいたいですね。会場にはアートも点在していますが、ベンチなどに注目してまとめても面白そう。
kt:まずはトイレ・休憩所・ステージのツアーの様子と、藤本さん、平田さん、吉村さんに聞くことができた総評について、記事でまとめていきます。
夜景と食にも注目!
oz:大屋根を中心に、夜はライトアップされてまたいいですよね。パビリオンも、日中とは表情が大きく異なるものもけっこうありました。

kt:期間中は、夜の22時まで会場は開いているのですよね。17時から入れる夜間券は、マジックアワーから夜景まで堪能できておトクだと思います。
oz:個人的には、enさんの「TECもぐもぐレポート」(食レポ)に期待しているのですが?

en:プレスデーではなんとか少し食したけど、なかなか時間がなくて堪能できず、心残りです…。
kt:大阪出身のymさんに前日の夜に串カツやさんで教えてもらったところでは、「くいだおれ」は、お店を変えながら少しずつ食べ歩くことを意味するみたい。その大阪の文化をワールドワイドな食事や軽食で体験できるのも、万博のもう一つの魅力ですよね。
それぞれが充実し、見どころ満載の大阪・関西万博。
各パビリオンなどのレポートや設計者へのインタビューも、順次アップしていきます。お楽しみに!