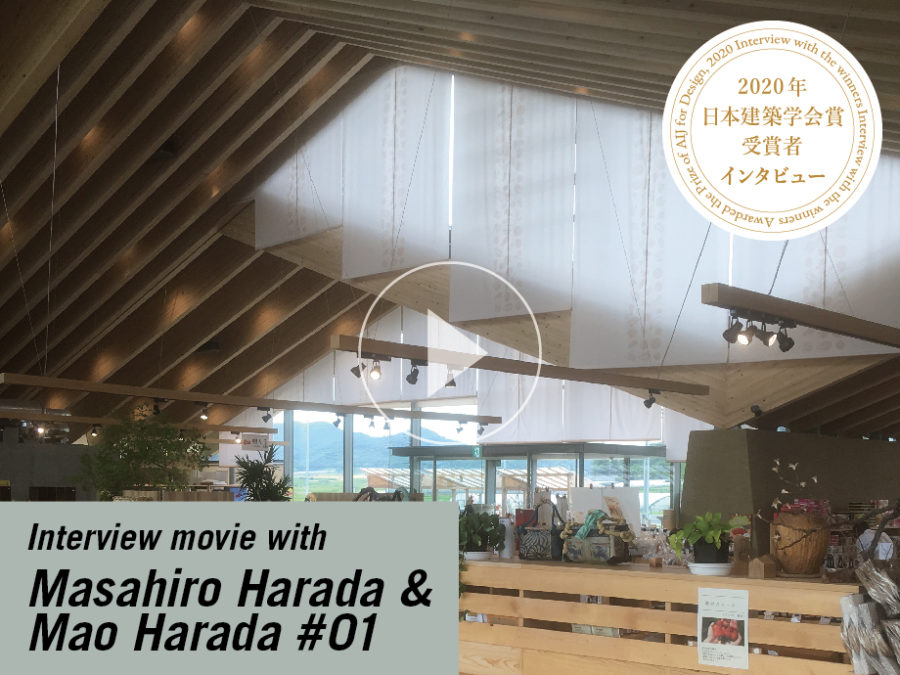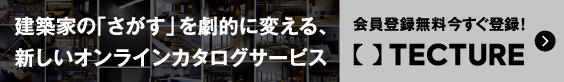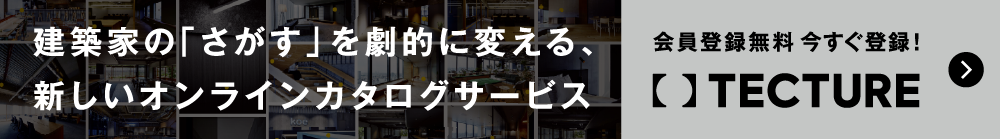『TECTURE』(https://www.tecture.jp/)には、日々多くの建築作品が投稿され、さまざまなクリエイターのアイデアや取り組みが共有されています。その膨大なデータの中から、作品の特徴やテーマに焦点を当てながら『TECTURE MAG』編集部視点で紹介していきます。
本記事では、傾斜地/旗竿地に建つ住宅を4件ずつピックアップ。土地自体は比較的安価に不動産市場に出回ることも多いですが、どちらも「扱いづらい」敷地としてさまざまな課題を抱えています。
敷地をどのように扱うかは、設計者の技術と創造力が試されるポイント。建物が地形や周辺環境に対していかに調和し、一見すると不利とも言える条件をどのように活かしているのか。傾斜地/旗竿地の可能性を見ていきましょう。
INDEX
傾斜地を住みこなす
- 地上の家 / ナノメートルアーキテクチャー
- 5つの小さな擁壁 / 武田清明建築設計事務所
- 八幡の二世帯住宅-更新される農地/構築される長屋- / 谷口弘和設計室|HTA
- Rural House / 葛島隆之建築設計事務所
旗竿地を住みこなす
- スプリットハウス / 成瀬・猪熊建築設計事務所
- 荻窪の住宅 / /360°
- 高尾の家 / Airhouse
- kusatsu-house / ALTS DESIGN OFFICE
傾斜地を住みこなす
日本の国土の約7割は、山地や丘陵地といった傾斜地が占めています。私たちの暮らしは平地にとどまらず、山間の集落や海に迫るような港町、川沿いの段丘上に広がる街並みなど、各地の風土や地形に適応しながら独自の風景を築いてきました。

高低差390mの急傾斜地に広がる落合集落。Photo: mitumal / iStock
戦後の爆発的な人口増加に伴い住宅需要が急増しますが、平地は農地や工業用地、都市インフラの整備に優先的に割り当てられ、居住スペースの確保が難しくなります。そこで都市近郊の丘陵地や山間部を切り開き、土地を平坦に造成したうえで住宅地として整備されるようになります。そして同時に住宅の規格化も進められました。

新興住宅地の街並み。Photo: photoAC
こうした宅地造成による土地と住宅の均一化は、今日にいたるまで合理的な住宅供給を可能にしてきた一方で、本来の地形がもつ豊かさや住まいの多様性を損なう側面もあります。
敷地は建物の形状や構造、そして住まい方そのものに大きな影響を及ぼす要素です。特に傾斜地には、平坦地にはない開放感や眺望、光や風の取り込み方など、その土地でしか得られない魅力と可能性が秘められています。ここでは、そうした傾斜地の特性を積極的に活かして設計された住宅事例をご紹介します。
〈地上の家〉ナノメートルアーキテクチャー

Photo: ToLoLo studio

Image: ナノメートルアーキテクチャー
住宅街に残された畑だった敷地の高低差約5mをそのままに居住空間を大胆にもち上げ、その下をピロティと緑化の場とした住宅。一定以上の緑地をもつことが必要な敷地で、庭はいらないという施主要望に対して庭と住居を明確に分けるのではなく、日々の動線と関係づけることで緑地を生活の一部に組み込んでいます。
TECTURE:https://www.tecture.jp/projects/5598
RECTURE MAG:https://mag.tecture.jp/project/20250407-house-off-the-ground/
〈5つの小さな擁壁〉武田清明建築設計事務所

Photographs: 浜田昌樹

Image: 武田清明建築設計事務所
奥行きの浅い高低差3.5mの地形を活かし、小規模の掘削により生まれた5つの小さな擁壁を内包した住宅です。内部はRC造と木造の上下2層構成。下層は一般的に床下基礎となる部分を居住空間としたもので、上層は大きな吹き抜けに柱梁が行き交い、多様な居場所をつくりながら将来的な増床を見越した設計となっています。
TECTURE:https://www.tecture.jp/projects/39
TECTURE MAG:https://mag.tecture.jp/project/20200604-house-with-5-retaining-walls/
〈八幡の二世帯住宅-更新される農地/構築される長屋-〉谷口弘和設計室|HTA

Photo: 笹倉洋平(笹の倉舎)

Image: 谷口弘和設計室|HTA
擁壁を建てるだけでも莫大な費用がかかるため、長年放置されていたひな壇状の敷地。周囲の住宅がそうであるように一般的には上下で分断される敷地ですが、その高低差を跨ぐ長い切妻屋根の二世帯住宅を設計しています。低い地盤に小さなボリュームを置き、高い地盤から長いボリュームを架け渡すことで、敷地造成をすることなく必要面積を確保し住宅を着地させています。
TECTURE:https://www.tecture.jp/projects/3568
TECTURE MAG:https://mag.tecture.jp/project/20240208-two-family-house-in-yawata/
〈Rural House〉葛島隆之建築設計事務所

Photo: 葛島隆之建築設計事務所

Image: 葛島隆之建築設計事務所
敷地内にある1m以上の高低差を造成せずに、スロープとして室内に取り込んでいます。2辺が長い三角形のような変形敷地をそのまま立ち上げたボリュームで、4つの中庭を点在させ、その間を蛇行するように道状のワンルーム空間が広がっています。屋根勾配も敷地の傾斜に沿って掛けられ、敷地の個性がそのまま形としたような平屋住宅です。
TECTURE:https://www.tecture.jp/projects/2294
TECTURE MAG:https://mag.tecture.jp/project/20230524-rural-house/
旗竿地を住みこなす
旗竿地とは、道路に接する部分が細長く伸び、その奥にまとまった広さがある土地のことを指します。その形が竿の先に旗がついたように見えることから、この名称が付けられました。
土地価格の高い都市部では、購入しやすい価格や広さに調整するため分筆が行われることあります。その際、建築基準法で定められた接道義務を満たしつつ使い勝手のよい形状に分けた結果、旗竿地が生まれます。

旗竿地のイメージ。Photo: photoAC
建物に囲まれているケースが多く、日当たりや風通し、周囲からの視線といった点で課題を抱えがちです。しかし一方で、一般的な整形地に比べて土地価格が抑えられる傾向があり、人気のエリアでもコストを抑えたい人にとって魅力的な選択肢となることがあります。
住環境においてはマイナスなイメージが多い旗竿地ですが、そこは設計者の工夫次第。ここでは、旗竿地が抱える課題を味方に付け、快適な住環境を実現した住宅事例をご紹介します。
〈スプリットハウス〉成瀬・猪熊建築設計事務所

Photo: 西川公朗

Image: 成瀬・猪熊建築設計事務所
1階と2階の間に360°の開口部を設け、採光とプライバシーを両立させています。構造壁がない中間層には、複数のブレースを設けることで水平力を担保。広々とした1階では、枝のようなブレース混じりの架構から光が降り注ぎ、木の存在感を味わうことができる、ヒューマンスケールの空間となっています。
TECTURE:https://www.tecture.jp/projects/2527
TECTURE MAG:https://mag.tecture.jp/project/20230220-split-house/
〈荻窪の住宅〉/360°

Photo: 吉田 誠

Image: /360°
四方を住宅に囲まれた住宅。敷地はもともと、この街区にとって中庭のような存在で、新しく建築をつくることでこの環境が壊れないことが意識されています。建物を少し地中に埋め、高さ1,500mmのデッキが覆うことで建物全体の存在感を抑えています。内部では地中熱により屋内環境が向上。生まれたレベル差を活かした多様な空間が生まれています。
TECTURE:https://www.tecture.jp/projects/4510
TECTURE MAG:https://mag.tecture.jp/project/20241118-house-in-ogikubo/
〈高尾の家〉AIRHOUSE

Photo: 矢野紀行

Image: AIRHOUSE
建物に囲まれながらも、南北の隙間から遠方に山々を望む敷地。中央にはLDKを配置した高さ5mの吹き抜け空間が広がり、個室や水回りの入った4つのボリュームが支えています。さらに5mの引き戸を抱えたインナーテラス、ガラス屋根のテラスと外部に対してグラデーションをつくることで、開放的な住空間を実現しています。
TECTURE:https://www.tecture.jp/projects/261
TECTURE MAG:https://mag.tecture.jp/project/20201127-house-in-takao/
〈kusatsu-house〉ALTS DESIGN OFFICE

Photo: 山田雄太

Image: ALTS DESIGN OFFICE
住宅と駐車場に囲まれた旗竿地で、南側にはマンションがあるため、南面を大きく開くとプライバシーを守ることが難しい敷地です。そこで、天窓に覆われた路地空間を挿入し、その路地空間に開くことで1日中緩やかな光を建物内に取り込めるようにしています。この路地空間は内外の境界を曖昧にし、実空間以上の奥行きを生み出しています。
TECTURE:https://www.tecture.jp/projects/4048
TECTURE MAG:https://mag.tecture.jp/project/20240620-kusatsu-house/
設計の制限ではなく、可能性として捉える
住宅をひたすらに量産する時代はとうに終わり、住まいに求められる価値はさらに多様化しています。
敷地の個性に向き合い、環境との関係を丁寧に築くように設計された住宅は、その土地ならではの空間を生み出します。傾斜地や旗竿地ではそれぞれの課題が明確であるからこそ、敷地に対する応答がより顕著に表れてくるように思います。
扱いが難しいとされる傾斜地や旗竿地ですが、今回紹介した事例からは敷地条件を制約ではなく、その土地のポテンシャルを引き出す可能性として捉える建築家たちの姿勢が伝わってきます。
text: Naomichi Suzuki


![[Interview]邸宅巣箱:”ネオ”地域密着型アーキテクト2/2](https://magazine-asset.tecture.jp/wpcms/wp-content/uploads/2025/01/22101006/top_thumbnail_20240709_001-1.jpg)





![[Interview]神谷修平:PLACELESS-普遍的な個別解-2/2](https://magazine-asset.tecture.jp/wpcms/wp-content/uploads/2025/02/19182725/top_thumbnail_20250219_002.jpg)