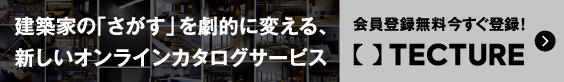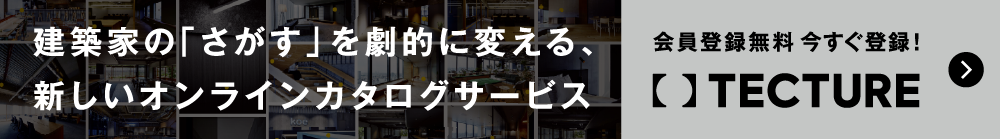ゲンロンカフェで開催されたシンポジウム「山本理顕 × 藤本壮介 万博と建築 ──なにをなすべきか」を受け、モデレーターをつとめた建築史家・建築批評家の五十嵐太郎氏にインタビューする連載特集企画。
万博の歴史を振り返った3回目に続き、建築史家・建築批評家の五十嵐太郎氏に、万博での開発や建築が活用されてきた経緯を教えてもらう。
トップ画像=〈オルセー美術館〉内観。1900年の万博に向けてつくられた〈オルセー駅〉をコンバージョンした建築。Photo: Taro Igarashi
INDEX
- 万博での開発を活かす都市
- 万博の後を見越した建築の姿
万博での開発を活かす都市
── 今年開催されるパリオリンピックでは、パリの中心部がレガシーとして活用される予定ですね。
五十嵐:
正直、東京オリンピック2020は、都市の魅力をうまく引き出せていなかったと思いますが、パリはセーヌ川で開会式を行うほか、これまでに積み重ねてきた都市のレガシーを巧みに利用していますね。
ゲンロンでも言いましたけど、パリではおよそ10年おきに何度も万博を開催していて、19世紀後半から20世紀前半にかけて、セーヌ川沿いにさまざまな展示施設、エッフェル塔、駅や橋をつくり、それらを残しました。万博は、良くも悪くも都市開発の手段として使われた側面があります。上海も万博を契機にウエストバンドを開発し、文化施設が並ぶエリアがつくられ、エンターテイメント企業が集まるメディアポートなどを整備しました。

▲パリで万博の開催に合わせてつくられてきた施設の例。左上:〈オルセー美術館〉(〈オルセー駅〉[1900年、設計:ヴィクトール・ラルー]をガエ・アウレンティが美術館として改修し1986年に開館)。右上:〈グラン・パレ〉(1900年、設計:アルベール・ルヴェほか)をピエール・ヴィヴィアンが改修し1964年に開館)。左下:〈プティ・パレ〉(1900年、設計:シャルル・ジロー)。美術展示場として建てられ、1902年にパリ市立美術館となる。右下:〈パレ・ド・トーキョー〉(1937年)。近代美術展示館として建てられ、1961年に美術館として再オープン。2002年に現代アートのための美術館として再オープン。2012年にはアンヌ・ラカトン&ジャン=フィリップ・ヴァッサルの設計により改修。Photo: Taro Igarashi
── 2025年大阪・関西万博でも、都市開発の側面があるのですよね?
五十嵐:
次の大阪万博ではインフラを整備すればIR施設がつくりやすいと考えられていると思うのですが、正確には万博の敷地とIRの敷地はまったく同じではなく隣なのですよね。そうであれば、別に壊さなくてもいいのではないかと思うのですが、きっとIRをフリーハンドに開発してもらうために壊す前提になっているのかなと思います。
ちなみに、現在のマカオの巨大化したカジノのエリアを訪れると(ラスベガス化しながらザハ・ハディドの設計によるホテル〈モーフィアス〉なども登場している)、大阪が今からIRを整備しても、アジア圏の競争に勝てる感じがしません。そうなると、結局はインバウンドではなく、せいぜい国内のギャンブル好きの場になるのではないでしょうか。
万博の後を見越した建築の姿
── 万博での開発が、その後に引き継がれるのはなかなか難しそうです。
五十嵐:
そういえば、この間久しぶりに「神戸ポートアイランド博覧会(ポートピア’81)」の会場となった地区を訪れたんです。〈神戸ポートピアホテル〉はインバウンドで賑わっているし、ホテルに面した博卵塊の広場などは今でも残っています。

神戸ポートアイランド博覧会(ポートピア’81)」の会場模型。Photo: Taro Igarashi

左:〈神戸ポートピアホテル〉(1981年、日建設計)。右:市民広場。Photo: Taro Igarashi
「花博」(国際花と緑の博覧会、1990年)があった大阪の鶴見緑地も、磯崎 新の建築が2つ、川崎 清の建築が1つ、日建設計が手がけた温室が今でも残っており、使われています。

〈国際陳列館〉(1990年、設計;磯崎新アトリエ)。Photo: Taro Igarashi

左:〈咲くやこの花館〉(1989年、設計:大阪市都市整備局+日建設計)、右:〈生命の大樹「いのちの塔」〉(1990年、川崎清+佐藤不二男+大林組本店)。Photo: Taro Igarashi
僕も日本館の基本理念の作文に少し関わった2005年の愛知での万博「愛・地球博」も、少しだけ残されていますけどね。当初、会場に使う予定ではなかった愛知青少年公園では、すべてを元に戻す現状復帰が求められたのですが、瀬戸会場では愛知万博が終わった後に、第一工房の設計した〈瀬戸愛知県館〉などは建築を減築して残すことが考えられていました。
次の大阪万博で話題にあがっているリサイクルやリユースは、愛知万博でもさんざん言われていたので、20年が経ってもあまり変わらないんだなと個人的には思いましたけど。

〈瀬戸愛知県館〉(設計:第一工房)の工事中の様子。Photo: Taro Igarashi
五十嵐:
建築に関して言うと、愛知では、万博の華と言われる外国館をすべてモジュール化したユニットの単位の切り売りに入れることになったので、つまらないものでした。
取り付けたファサードだけデザインすることをFOAがしていましたが、同じ頃にできた〈金沢21世紀美術館〉のほうが注目度は高く、建築の関係者は万博ではなく、そちらに向かったと思います。また残念ながら、現代アートの作家もほとんど参加していませんでした。愛知に比べると、今回は面白そうな若手建築家がたくさん入っているので、期待しています。

愛知万博「愛・地球博」外国館(グローバル・コモン)の例。左:チェコ共和国館、右:スペイン館(設計:アレハンドロ・サエラ・ポロ)。Photo: Taro Igarashi
(5/5に続く)




![[大阪・関西万博]万博行ったら見ておきたい海外パビリオン特集!](https://magazine-asset.tecture.jp/wpcms/wp-content/uploads/2025/07/07174850/0707_1-900x676.jpg)



![[Interview]神谷修平:PLACELESS-普遍的な個別解-1/2](https://magazine-asset.tecture.jp/wpcms/wp-content/uploads/2025/02/19164726/top_thumbnail_20250219_001.jpg)
![[Interview]神谷修平:PLACELESS-普遍的な個別解-2/2](https://magazine-asset.tecture.jp/wpcms/wp-content/uploads/2025/02/19182725/top_thumbnail_20250219_002.jpg)