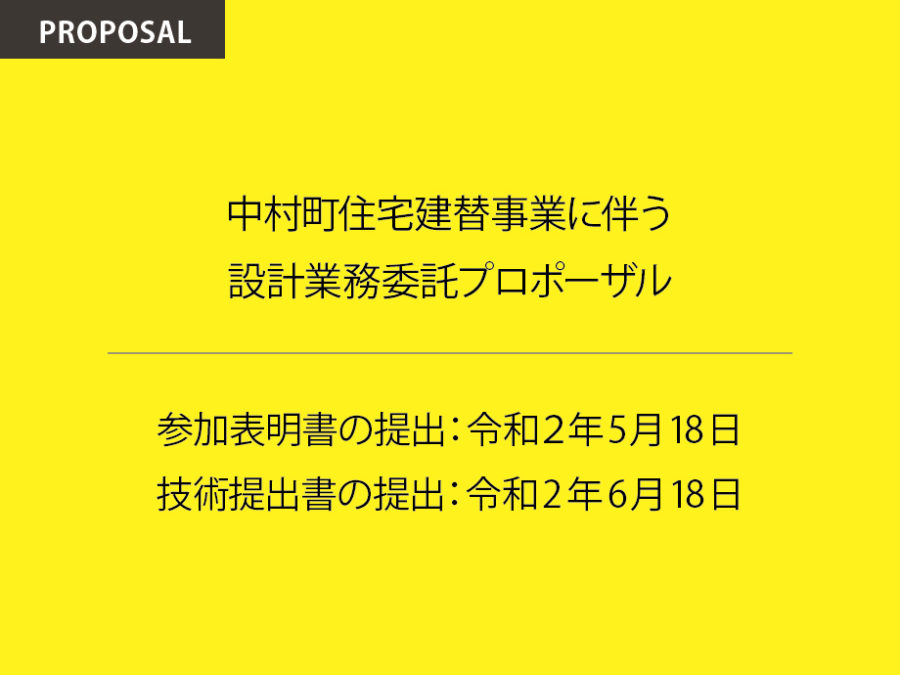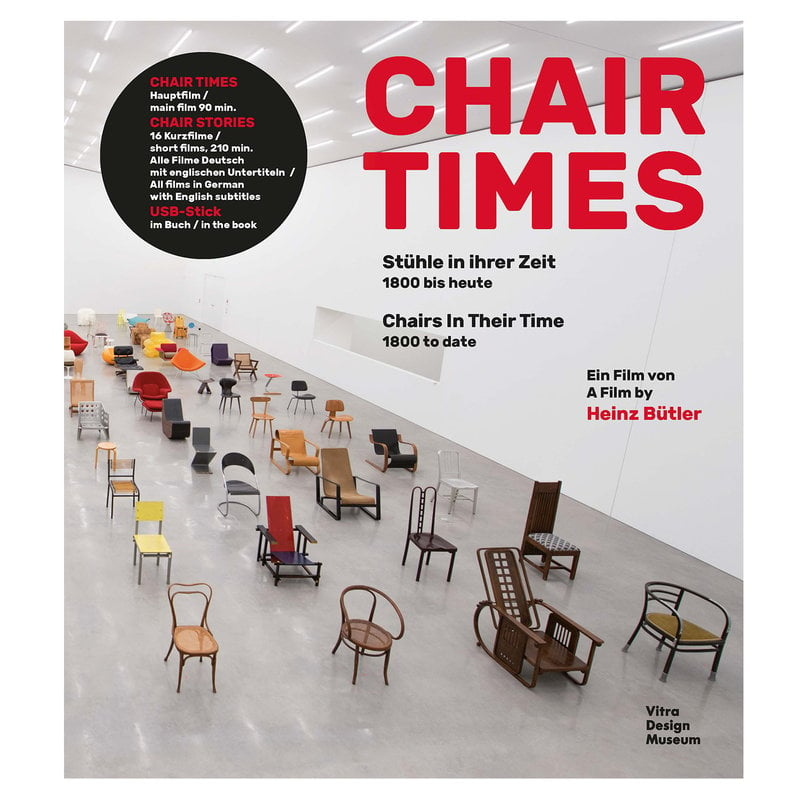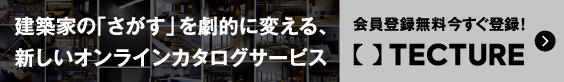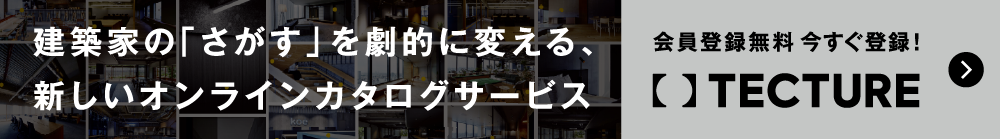COMPETITION & EVENT

東京都庭園美術館「そこに光が降りてくる 青木野枝/三嶋りつ惠」展
[Report] 青木淳 展示監修、2人作家の鉄とガラスの作品と"アール・デコの館"をゆるやかにつなぐ
東京・白金台5丁目の東京都庭園美術館にて、「そこに光が降りてくる 青木野枝/三嶋りつ惠」展が開催されています。会期は2月16日まで。
本展は、現代美術作家の青木野枝(1958-)と三嶋りつ惠(1962-)の両氏が、本展のために作品を制作・展示し、”アール・デコの館”と称される東京都庭園美術館(旧朝香宮邸、以下庭園美術館と一部で略)の各所にて展開するもので、新たな視点でアール・デコの装飾空間を照らし出そうという試みです。
『TECTURE MAG』では、オープン前に行われたプレス内覧会を取材。会場写真を中心に、本展をレポートします(会場写真はすべて、TEAM TECTURE MAGの撮影)。

東京都庭園美術館本館 外観 朝香宮邸として1933年(昭和8)に竣工した建物
“一期一会” 本展のための特別な展示
両氏がこれまでの代表作などにも用いているそれぞれの素材、青木野枝作品における”鉄”と、三嶋りつ惠作品における”ガラス”は、自然からの恵みであるとともに、何千年という時を重ねて人類がつくりあげてきた技術から生み出されるもの。そして、それらは、本展の会場である旧朝香宮邸(美術館 本館)の要所に見られる、シャンデリアやレリーフ、扉上のタンパンといった装飾品の素材でもあります。本展の開催にあたり、両氏は何度も庭園美術館を訪れ、装飾空間との対話を重ね、展示プランの策定に取り組んだといいます。
本展では、両氏の新作のほか、作品の制作工程が分かる映像やインタビュー映像などの貴重な資料も披露されています。
本展の見どころ
光に対して特別な想いを抱いてきた、2人の現代作家による大型インスタレーション
精力的な活動を続ける2人の女性作家が、本展のために特別に作品を準備し、展示を構成します。
青木野枝は、重い素材とされる鉄に向き合い、鉄を溶断する時にあらわれる内部の「透明な光」から様々なインスピレーションを得てきました。一方、三嶋りつ惠は、私たちの身の周りに溢れる光の表情に心を寄せて、自身のガラス作品を通して「光の輪郭」を描き出そうと試みてきました。
光に対する意識や向き合い方は異なる二人ですが、光に思いを馳せて生み出された作品が、陰影に富んだ空間に広がります。昼は自然光が差し込み、夕暮れには温かな室内照明が灯る。時間ごとに、季節ごとに、絶えず変化する展示風景をぜひご鑑賞ください。アール・デコの館を舞台に、時を超えて響き合う”鉄”と”ガラス”
庭園美術館本館の最初の住人である朝香宮夫妻は、洋行先のフランスで目にしたアール・デコの様式美に魅了され、その精華を取り入れた自邸を1933年に完成させました。各室ごとにさまざまな素材を用いた装飾性豊かな朝香宮邸の空間において、アール・デコの造形のエッセンスを雄弁に物語るのが、鉄とガラスという2つの素材です。
フランスのアーティストであるルネ・ラリック(1860-1945)や、鉄工芸家のレイモン・シュブ(1891–1970)らが手がけた歴史的な装飾空間に、青木野枝と三嶋りつ惠の鉄とガラスの作品が作家自身の手によって配置され、時を超えた特別な競演が実現しています。
三嶋りつ惠作品 展示風景(1階部分)

本館1階(大広間)展示風景 / 三嶋りつ惠《光の海》2024 ガラス
「《光の海》と名付けたこの作品は、職人さんたちとのいうなれば闘いを経て生まれたものです。1933年にこの朝香宮邸がつくられ、人を招き、もてなして、楽しんでもらっていた、そんな光景をイメージして構成しました。作品の配置は、現場にて、作品どうしの響き合いといったものを感じとりながら置いていきました。個数は、私が心惹かれたこの部屋の天井のライトの個数とほぼ同じ。この部屋からつながっている大階段を上がった先の広間での展示もそうですが、この館の空間と会話をする、訪れた人同士でも会話をする、そんな展示になっていればいいなと思います。」(プレス内覧会での三嶋りつ惠氏による作品解説を『TECTURE MAG』にて要約)

三嶋りつ惠《光の海》(部分)

本館1階(小客室)展示風景 / 三嶋りつ惠《宇宙の雫》2022 ガラス、銀

本館1階(小食堂)展示風景 / 三嶋りつ惠《STANDING》2021 ガラス
青木野枝作品 展示風景(1階部分)

本館1階(大客室)展示風景 / 青木野枝《ふりそそぐもの/朝香宮邸 I》2024 鉄、ガラス

本館1階(大食堂)展示風景 / 青木野枝《ふりそそぐもの/朝香宮邸 II》2024 鉄、ガラス

本館1階(第2階段前)展示風景 / 青木野枝《Untitled》1981 鉄
隠れた見どころ・青木 淳氏による展示空間
本展には、建築家の青木 淳氏が参加、展示監修を担当しています。どの部屋でどちらの作家が展示を行うかといったバランスを図るなど、展示構成にも関わっているとのこと。
とはいえ、この美術館を何度か訪れていていても、青木氏の「仕事」に気づくことができる人は少ないでしょう。ごく自然に、本展のための展示空間として馴染んでいるからです。
「青木野枝さんと三嶋さんは、鉄とガラスと扱う素材が異なり、作品のあり方そのものや、ものづくりへのアプローチも異なる。その2人が同じ空間で展示を行う本展は、どのようなかたちでこの2人の共演が成立するのかということに挑戦した展覧会です。ここで求められる僕の役割は、並び立つ2人の現代作家、そしてこの旧朝香宮邸とアート作品とのあいだで調和を図ることだと考えました。
本展は、空間としての質が元から色濃くある、旧朝香宮邸の部屋に作品が配置されています。いわゆる美術館のホワイトキューブに展示するのとは勝手が違う。もちろん、お2人とも、会場の場所性といったものにとても敏感で、ホワイトキューブ以外の空間での展覧会実績も国内外で多数ありますし、本展のように、展覧会にあわせて展示台を自身で用意することもできる。そういったなかで、僕は、旧朝香宮邸という、モノ言わぬ建築物の”気持ち”を代弁してみようと考えました。できる限り、元々ある空間の中に、違和感なく、自然なかたちで作品が置かれているようにする。
例えば、本館の大食堂などほとんどの部屋は元々は木の床なのですが、通常はカーペットで養生されています。けれども、元々は朝香宮御一家は木の床で生活していたはずで、2階の姫宮居間はヘリンボーンが張られているなど意匠性も高い。そういった美しい床と、旧朝香宮邸の内装がもっている豊かな色彩にもあわせた本展のための床を用意して、大食堂の床に敷き詰めています。知らない人がみれば、元からこういう色の床だったのではないかと思うような、そんな精度を目指しました。」(プレス内覧会冒頭の関係者挨拶およびその後の青木氏へのインタビューを『TECTURE MAG』にて要約)

青木野枝《ふりそそぐもの/朝香宮邸 I》2024 鉄、ガラス
大客室の床面は青木氏が既製品の中から色を厳選したもので、その上に作品が直に設置されている

青木野枝作品《ふりそそぐもの/朝香宮邸 II》が設置された大食堂の展示(通常はカーペットが敷かれており、青木氏は「ここで僕がやった仕事を控えめに言うと、”オレンジ色の床を敷いただけ”です」と笑った)
三嶋りつ惠作品 展示風景(2階部分)

本館2階(2階広間)展示風景 / 三嶋りつ惠《光の場》2019 ガラス、アルミニウム

三嶋りつ惠《光の場》(部分)

本館2階(北の間)展示風景 / 三嶋りつ惠《TABLINO》(部分)2024 ガラス

本館2階(姫宮寝室)展示風景 / 三嶋りつ惠《CLISANTEMO》2024 ガラス

三嶋りつ惠《CLISANTEMO》2024 ガラス

本館2階(姫宮居間)展示風景 / 三嶋りつ惠《CLISANTEMO》2024 ガラス

本館2階(姫宮居間)展示風景 / 三嶋りつ惠《CLISANTEMO》2024 ガラス

本館2階(妃殿下居間)展示風景 / 三嶋りつ惠《MILLELUCI》2013、《RULLO》2024 ガラス

本館2階(ベランダ)展示風景 / 三嶋りつ惠 《SPIN》2024 ガラス(手前の作品)、《INFINITO》2023 ガラス(奥の作品)

本館2階(妃殿下寝室)展示風景 / 三嶋りつ惠 制作をめぐる資料

本館2階(書斎)展示風景 / 三嶋りつ惠《MONDO》2023 ガラス
青木野枝作品 展示風景(2階部分)

本館2階(若宮寝室)展示風景 青木野枝《ふりそそぐもの/朝香宮邸 III》2024 鉄、ガラス、銅線

本館2階(合の間)展示風景 / 青木野枝《ふりそそぐもの/朝香宮邸 IV》2024 鉄、石炭

本館2階(若宮居間)展示風景 / 青木野枝《ふりそそぐもの/朝香宮邸 V》2024 鉄、石鹸

青木野枝《ふりそそぐもの/朝香宮邸 V》(部分)

本館2階(第一浴室)展示風景 / 青木野枝《ふりそそぐもの/朝香宮邸 VI》2024 鉄、石鹸

本館2階(金庫室)展示風景 青木野枝《ふりそそぐもの/朝香宮邸 VII》2024 鉄、紙、銅線
青木野枝作品 展示風景(新館ギャラリー1)

新館ギャラリー1 展示風景 青木野枝《ふりそそぐもの—赤》2024 鉄、ガラス

青木野枝《ふりそそぐもの—赤》2024 鉄、ガラス
青木野枝氏にとって、作品の中で用いる「赤」は特別な色であり、これまではある強い思いがある長崎でしか発表しておらず(そのほかの作品では透明のガラスが嵌め込まれている:本展フライヤーを参照)、本展は異例ともいえる貴重な展示となります。
新館のほか、本館に展示されている一連のシリーズ作品《ふりそそぐもの/朝香宮邸》について、青木氏は次のように語っています。
「これらの大型作品は、2つから4つのパーツに分割して、4トン車6台分というボリュームで搬入しました。本館の展示室には男性複数人で運び込み、そのあとは現場で、ボルトナットで留めて仕上げていきました。設営中、2階でひとり、石炭の山を1つ1つ積んだりしているうちに、だんだんと、ここで暮らしていた人々の当時の暮らしに思いを馳せるようになりました。建物が完成するまでの8年間は、朝香宮妃殿下がフランスとの手紙のやりとりを何度も交わしたと聞いています。そうした『どうしてもこれをつくりたいんだ』という強い思いと、私自身の『つくりたい』という気持ちが、時を超えて、シンクロするような感覚を覚えました。実は、アール・デコの館はあまり好きではありませんでしたが、建物への親しみもどんどんと増していきました。1933年(昭和8)の日本と世界は、その後の世界大戦へと続くいろいろなことがあった年です。そんな歴史的な背景や、この場所で私が感じとった世界のようなものが、この《ふりそそぐもの/朝香宮邸》という新作シリーズにはあらわれています。」(プレス内覧会での青木野枝氏による作品解説を『TECTURE MAG』にて要約)
作家へのインタビュー映像は YouTubeでも公開中
#東京都庭園美術館YouTube:青木野枝 インタビュー「そこに光が降りてくる 青木野枝/三嶋りつ惠」展(2024/11/30)※期間限定公開
#東京都庭園美術館YouTube:三嶋りつ惠 インタビュー「そこに光が降りてくる 青木野枝/三嶋りつ惠」展(2024/11/30)※期間限定公開
「そこに光が降りてくる 青木野枝/三嶋りつ惠」展 開催概要
会期:2024年11月30日(土)より開催中、2025年2月16日(日)まで
会場:東京都庭園美術館 本館+新館
所在地:東京都港区白金台5-21-9(Google Map)
開場時間:10:00-18:00(入館は閉館の30分前まで)
休館日:月曜
観覧料:一般 1,400円、大学生(専修・各種専門学校含む)1,120円、中学生・高校生 700円、65歳以上 700円
※オンラインによる事前予約制を導入
問い合わせ先:050-5541-8600(ハローダイヤル、受付時間 9:00-20:00 ※休館日を除く)
東京都庭園美術館ウェブサイト
https://www.teien-art-museum.ne.jp/
関連企画
本展の会期中は、新館のカフェ・レストランなどでは、本展からイメージしてつくられたコラボレーションメニューも販売されます。